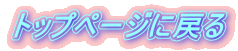富山県富山市
*参考資料 『越中中世城郭図面集』①(佐伯哲也) 『日本城郭体系』
*参考サイト 城郭放浪記
高嶺城(富山市八尾町高嶺)
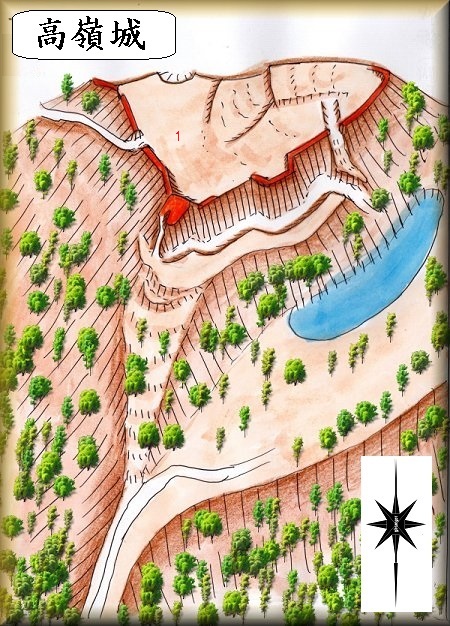 *鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。
鷹嶺城の場所。 作業林道の入口。
高嶺城は、八尾町新名の比高40mほどの山稜に築かれていた。
北側から城の手前まで続く未舗装の林道があるので、これを通って行けば城内近くまで簡単に到達できる。
林道の入口は上記の場所である。入口付近に路肩のスペースがあるので、車はそこに停めて置くことができる。
ここから未舗装林道を300mほど進んで行くと林道は途絶えてしまう。
その先は平場となっており、左手の先が一段高くこんもりとしている。
このこんもりとした部分が城址なので、そちらを目指していく。
ところが、ここからは道はなく、ヤブと化した緩斜面を頑張って登って行くしかない。
すると城の北側の横堀の所に出た。
左手に城内に通じる道がある。これを登ると城の北端の櫓台の所に出た。
城は単郭のもので、三角形状をしている。
南側を除く2方向には土塁が盛られており、虎口も開口している。
北側の城塁には張り出し部分があり、それがとても目立っている。
郭内部の削平はきちんと行われておらず、陣城的な雰囲気もある。
郭内部もヤブがひどく、夏場では見通しがよいとは言えない。
見事な遺構が残っているのだが、どこもかしこもヤブだらけなのが残念である。
『三州城跡集』によると、高嶺城には神保氏の部将がいたという。
しかし、その武将名や事績など、詳しいことについては不明である。
 |
 |
| 林道入口。 |
林道の終点。左手のこんもり高いところが城址。 |
 |
 |
| 横堀 |
横堀 |
 |
 |
| 郭 |
土塁 |
 |
 |
| 城塁と横堀 |
城塁 |
 |
 |
| 郭 |
城塁と横堀 |
 |
 |
| 櫓台 |
横堀 |
|
下笹原城(富山市八尾町下笹原)
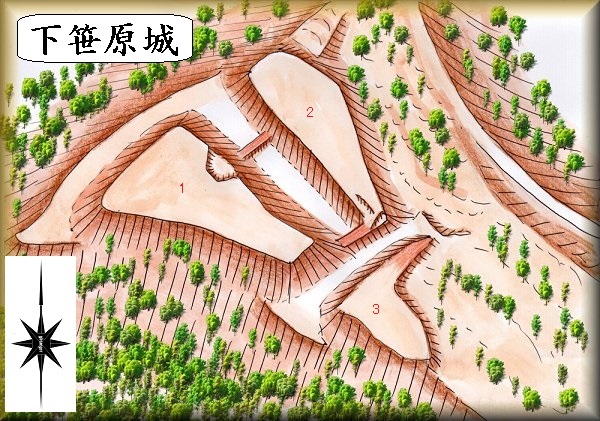 *鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
下笹原城の場所。 城内への入口。
下笹原城は、富山市立八尾小学校の南方、2つの河川に囲まれた比高50mほどの山稜に築かれていた。
東側を道路が通っており、そこからの比高は20mほどである。
城への入口の所に案内表示があるので、そこから登って行ける。登城口のすぐ脇には墓地があり、車はそこに停めさせていただいた。
登城道を登って行くとすぐ左手に土手が見えてくる。これが城塁のように見えるのであるが、実際の城域はもう少し先に進んで行った所の西側上である。
西側上に登って行くと堀切が見えてくる。城域の南端を区画するものである。
その南側には3の土壇があるのだが、これは馬出のようなものだったであろうか。
その先に大堀切があって1郭と2郭とを区画している。
ここから西側に登った三角形状の郭が1郭である。
1郭の中央部には枡形状の虎口があり、その下の土橋と接続していたようである。
コンパクトながら堀はしっかりと大きく掘られている。
『泉達録』に「越後より越中攻めの時、神保の将住す」と記載されているので、高嶺城と同様に神保方の支城の1つだったと考えられるが、武将名や詳しい事績などは分かっていない。
 |
 |
| 登城道入口 |
登城道 |
 |
 |
| 3郭土塁 |
堀切 |
 |
 |
| 堀切 |
堀切 |
 |
 |
| 堀切 |
郭 |
 |
 |
| 郭 |
枡形虎口 |
 |
 |
| 堀切 |
堀切 |
 |
 |
| 土橋 |
堀切 |
|
城ヶ山公園(富山市八尾町諏訪町)
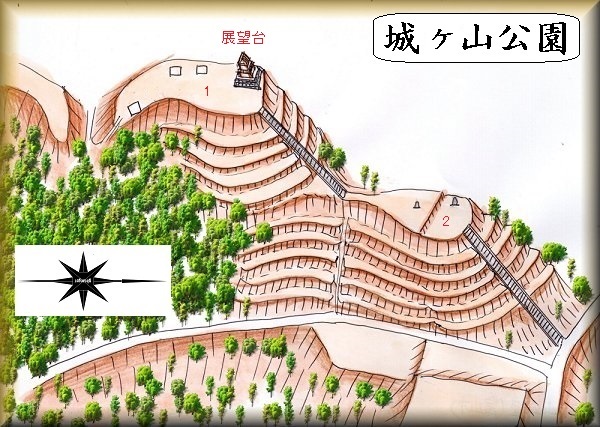
城ヶ山公園の場所。
下笹原城jの北西側、八尾の市街地の南にそびえているのが城ヶ山で、現在城ヶ山公園として整備されている。
市街地からの比高は90mほどあり、中腹部分まで車で登って行くことができる。
城ヶ山という名称からして、城址の候補地と想定できそうな場所なのであるが、なぜか遺跡地図などには採用されていない。
城ヶ山でありながら、城址としては認定されていないのが不思議である。
ただ、実際に歩いてみると、山城と言ってもいいような地形にあることは確かである。
しかも山頂部には模擬天守風の展望台まで建てられている。
そして側面部には多数の帯曲輪が造成されている。
これらがすべて城郭遺構であるとは考えがたいが、城郭的な光景であることには間違いない。
城ヶ山という名称と言い、城があった場所と認定してもよいのではないだろうか。
城ヶ山の城主等、歴史については未詳である。
 |
 |
| 2郭への石段 |
帯曲輪群 |
 |
 |
| 帯曲輪群 |
帯曲輪 |
 |
 |
| 2郭 |
2郭 |
 |
 |
| 1郭へ |
帯曲輪群 |
 |
 |
| 1郭城塁 |
1郭 |
 |
 |
| 1郭の展望台 |
展望台 |
 |
 |
| 帯曲輪群 |
帯曲輪群 |
 |
|
| 東側からの遠望 |
|
|
猿倉城(風の城・富山市舟新)
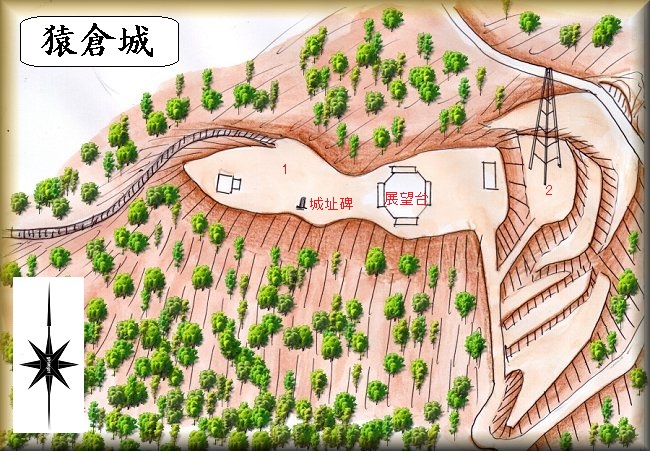 *鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
猿倉城の場所。
猿倉城は神通川の東側にそびえている比高240mほどの急峻な山稜に築かれている。
地図などには「風の城」と掲載されており、一帯は風の城公園となっている。
城内に展望台が建てられており、そこまで車道が付けられている。だから上まで車で行くつもりでいたのだが、車のナビで猿倉展望台をインプットしたところ、展望台の所に来てしまった。
ここには駐車場やトイレがあるのだが、ここから山頂までは比高70mほどあり、長い階段を登って行くことになる。
失敗した、と思いながらも頑張って階段を登って山頂に到達した。
山頂にも南東側に車道が付けられていたので、別ルートを取れば車で城内まで乗り入れることもできるはずである。
車道で1郭に登ってきたあたりには車を停めて置けるスペースもある。
1郭は東西に長く、中央付近に城址碑が建てられていた。
また大きな展望台も建てられている。比高がかなりあるので、眺望はとても利いている。
西端には猿倉社二神神社が祀られている。
東側に一段低く鉄塔が建てられているのが2郭である。
その下にも腰曲輪が数段形成されていた。
元亀2年(1571)、飛騨の塩屋筑前守秋貞が当地域まで進出してきて、猿倉山に登って城の普請をしたという記録がある。
猿倉城はこの時に築かれたものと考えられるが、それ以後の歴史については未詳である。
 |
 |
| 猿倉展望台から |
長い階段を登って行く |
 |
 |
| 階段が続く。 |
1郭に到達・・・看板のクマの顔が怖い・・・。 |
 |
 |
| 猿倉社二神神社 |
城址碑 |
 |
 |
| 展望台 |
城址碑。こちらは「風の城」とある。 |
 |
 |
| 眺望 |
1郭への車道 |
 |
|
| 眺望 |
|
|
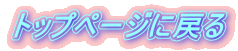
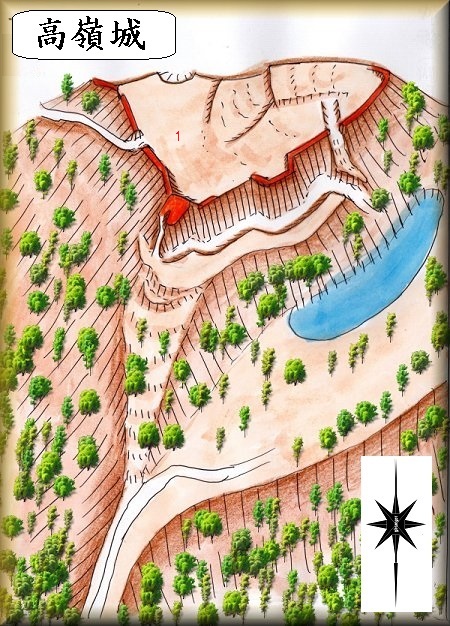 *鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。











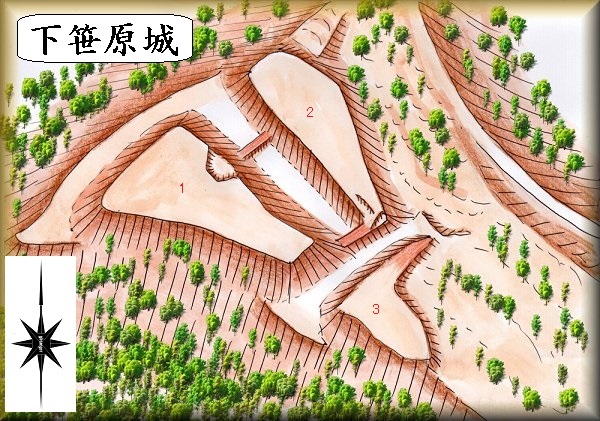 *鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。













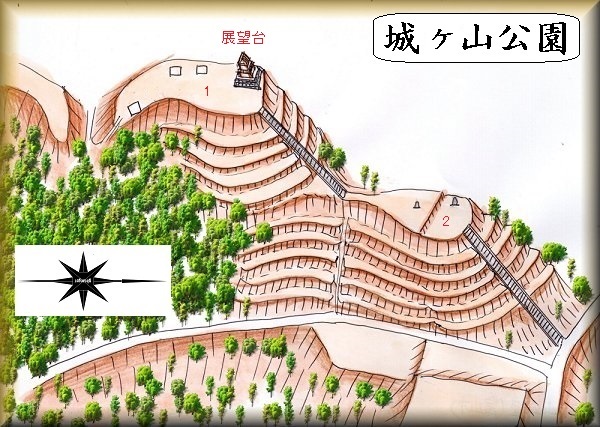















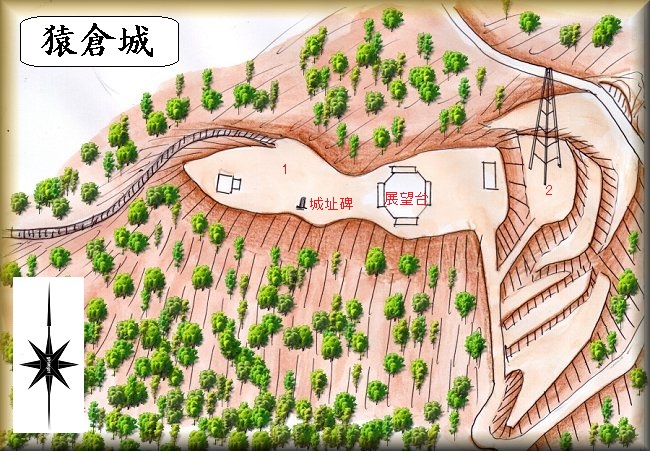 *鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。