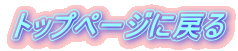*参考資料 「夷隅の城」(小高春雄)
大野城(鶴ヶ城・いすみ市大野字要害)
 大野城は鶴ヶ城とも呼ばれ、夷隅川の湾曲部分の内部にある台地を利用したものであり、河川を堀として巧みに利用している。またこの台地そのものが岩盤で形成されており、何ヶ所かに見られる堀切も、岩盤をダイナミックに断ち切ったものである。こういう堀切は正木系、土岐系の城郭でよく見られるものである。
大野城は鶴ヶ城とも呼ばれ、夷隅川の湾曲部分の内部にある台地を利用したものであり、河川を堀として巧みに利用している。またこの台地そのものが岩盤で形成されており、何ヶ所かに見られる堀切も、岩盤をダイナミックに断ち切ったものである。こういう堀切は正木系、土岐系の城郭でよく見られるものである。
八幡神社のある台地上(「夷隅の城」では「蝶が羽根を広げたような地形」とあるが、まさにそんな感じ)が主要部である。台地上は一面の畑地となっているが、もともとは郭を2つに区画する堀切が南北に入っていたらしい。その痕跡は、南端と、北端で見られるのであるが、この湾曲していたらしい堀そのものの構造は完全には復元できない。深さ2m程度の小規模な物であったことがわかっているようだが。それはともかくとして、この台地上の2つの郭が城の中心であったということは間違いないであろう。
この1,2郭の北側下には幅15mほどの腰曲輪がある。「夷隅の城」では、これはもともとは横堀であったろうと推測している。ここから1,2郭までの高さは5mほど、またこの部分の城塁の、下の郭からの高さは4mほどしかないが、城塁は岩盤を垂直に削っており、かなりの防御力があったのではないかと推察できる。
1郭の北西端の尾根には深い岩盤堀切がある(堀切3)。そして、この部分の特徴は、先端近くに櫓台状の部分を置き、それを取り巻くように堀切を入れていることである。どういう防御思想であったのか明確にはできないが、尾根防御のための施設がここに置かれていたのだと思われる。
2郭の南西端は、現在道路によって大幅に削れられてしまっているが、かつてはこの方面も尾根続きであり、こちら側にも岩盤を大胆に削った堀切2が見られる。しかし、こういう岩盤堀切を造るのって大変だったろうなあ・・・・。
2郭の下の3郭辺りは耕作地となっていた関係で、地形がかなり改変されていると思われ、城の形態がどのようであったかよく分からない面が多い。というのも、この部分には微妙な段差があちこちに見られるのだが、これらが城郭構造物として一体化して見えないのである。おそらく、基本的には単純構造で、周囲を土塁と堀で囲んでいたくらいだったのではないかとは思うのであるが。
このように大野城は規模もそこそこ大きく、堀切などもきちんと入れている。戦国末期の城郭である。
 |
 |
| 夷隅川沿いに見た大野城。川が湾曲して堀の役目を果たしている。右手奥の高台が1郭にあたる。 |
北側に入る切り通し(堀切1)。深さ6mほどあり、岩盤を削ったものである。 |
 |
 |
| 3郭と4郭とを隔てる堀の跡。「堀の田」という名称であるらしい。 |
神社の参道から1郭の城塁を見た所。高さは5mほどだが、岩盤を垂直に削っており、防御性は高い。右側の腰曲輪はかつては横堀であった可能性もある。 |
 |
 |
| 南西側の堀切2。深さは5mほど。岩盤を掘り切ったものである。この堀切を分断するようにして車道が通っている。 |
北東側の堀切3。深さ6mほど。やはり岩盤を掘りきったもので、まともによじ登るのは難しい。 |
大野城は、かつては狩野氏の伊保城と関連付けて説明されることが多かったが(つまりこここそが狩野氏の住んでいた伊保城ではなかったかということ)、狩野氏は応仁元年に城を攻め落とされていることと、現在見られる大野城の遺構は戦国末期のものであると見られることなどから、狩野氏の居城をそのまま大野城とするには疑問を持たれるようになってきている。
そのため「大野城発掘調査報告書」では、「大野城には、二つの時代が存在しており、狩野氏の居城としての時代、土岐氏(あるいは正木系)の城郭として戦国末期に取り立てられた時代に分けて考えるべきである」といったように述べている。
しかし、戦国期以前の狩野氏の居城がここであったかどうかについては、何の確証もないのが実態である。(「夷隅の城」では「引田館こそそうではないか」と言っている。) 現在見られる大野城の遺構からは、戦国末期に築城、あるいは大幅な改修を受けた城ということが明らかである。したがって、大多喜正木氏か、土岐氏かのいずれかと関連付けて考えるべきである。
永禄期には、正木氏は行川辺りにまで支配権を行使しており、当地域が境目になっていた可能性が高いという。夷隅川を前面の要害として意識していたとすれば、この城は土岐氏に対する正木方の城郭ということになるだろう。
正木氏と土岐氏は、天正3年頃、抗争を行っており(八幡城の項、参照)、万木城の向城として、八幡城を取り立てたりしている。そうした両者の抗争の過程において、境目の城として取り立てられ活用されたのが大野城ではなかったかと考えられる。(「夷隅の城」参考) |
国府台城(いすみ市国府台字細廓)
 夷隅川にかかる橋のたもとに城はある。ファミリーマートのちょうど正面の高台である。しかし、規模はそれほど大きなものではなく、五柱神社のある「細廓」という部分と、その南側の畑地になっている2郭とが城の中心となる。2郭の南側には堀切を入れることによって、台地基部との間を区画しているが、この堀切もかなり幅を広げられ形を変えてしまっているようで、もとはもう少しメリハリの効いた形態のものではなかったかと想像される。現在、この堀切から2の郭内に上がるための切通しの道が付けられているが、これはこの上のアンテナに行くための道であろう。
夷隅川にかかる橋のたもとに城はある。ファミリーマートのちょうど正面の高台である。しかし、規模はそれほど大きなものではなく、五柱神社のある「細廓」という部分と、その南側の畑地になっている2郭とが城の中心となる。2郭の南側には堀切を入れることによって、台地基部との間を区画しているが、この堀切もかなり幅を広げられ形を変えてしまっているようで、もとはもう少しメリハリの効いた形態のものではなかったかと想像される。現在、この堀切から2の郭内に上がるための切通しの道が付けられているが、これはこの上のアンテナに行くための道であろう。
1郭の東側下5mほどの所に3の腰曲輪がある。この腰曲輪の先端部分は切り通しになっており、そこから想像すると、この腰曲輪そのものがもともとは横堀であったとも推測できる。もしそうだとしたら、後世、耕作地にするために地勢を均して腰曲輪状にしたものということになるのであろう。この腰曲輪から下の道路までの高さは3mほどである。おそらくその下の部分にも堀はあったのであろうが、現在では痕跡もない。この3の腰曲輪の脇に神社に上がるための参道が付けられているが、その北側下には一軒の民家があり、このお宅ができたことによって、周辺の地形はだいぶ改変されている。もともとはこのお宅の建っている辺りから城塁に沿って上がる道があったというのだが、それが本来の登城道というべきであるのかもしれない。
西側下8mほどの所にも4の腰曲輪がある。ここも一部は横堀状になっているらしいが、下まで降りていかなかったので確認できていない。もっとも、こちら側は河川の断崖に面しているので、それほど防御に気を遣う必要もなかったのかもしれない。それよりも、夷隅川は水運にも利用されていたであろうか、船着場に下りていくための道がこの辺りからついていたのではないかと思われる。
国府台城は規模は小さく、夷隅川の渡河点を押さえるための城郭であったのではないかと考えられる。
 |
 |
| 台地基部との間を区画する堀切。後世、かなり幅を広げて改変されているようである。 |
1郭に建つ五柱神社。 |
 |
 |
| 国府台城北側の橋の上から見た夷隅川。写真左側の断崖の上が国府台城跡である。 |
1郭東下の腰曲輪を上から見た所。現状では腰曲輪であるが、もともとは横堀であった可能性がある。 |
「房総治乱記」のような軍記物では、国府台城は矢竹城、鶴ヶ城と並ぶ、万木土岐氏の有力な支城となっている。上記の通り規模は小さいが、水陸の交通の重要な地点に位置しているので、確かに土岐氏にとって重要な支城であったとみてよさそうである。
「房総志料」には「三階図書介居城」とあるらしい。三階氏は土岐氏の家臣で、現在、この子孫であるといわれる中村家の系図では、三階義政の三代後の義高の時代に、土岐氏滅亡という事態になり、三階氏も地元に土着し、妻方の姓である中村を名乗るようになったのだということである。この三階氏が城主であったと一応見てよいだろう。 |
八幡城(権現城・いすみ市権現堂字向台)
 権現堂に八幡神社があるが、その北側の比高15mほどの台地全体が八幡城の跡である。
権現堂に八幡神社があるが、その北側の比高15mほどの台地全体が八幡城の跡である。
城は台地を利用して数段の削平地を重ねたものである。斜面はしっかり切岸となっているので、比高差はそれほどでもなくとも、そこそこの防御力を発揮することはできたであろう。
1の郭が最高所に当たり、ここが主郭であると一応考えてよいだろう。ただし、この部分は、向側の万木城からすると、正面にかなり近い位置になり、その背後の3の郭などからすると、防御壁のようにもなっている。だが、城がもともと戦闘色の強い向城であるのだとしたら、そういう主郭もあったよいだろう。
3の郭の西には一段低く4の郭、その西に2mほど高く5の郭、そして次には2mほど低く6の郭というように、わりと凸凹した郭の配置をしているのが印象的である。これらの連郭群の北側には段々に郭が低くなって配列されていて、その先の低地が北に向かって開けているので、防備的には非常に不利な構造に見える。
ところが、この先には大きな溜池があるのである。この溜池が戦国期から存在していたとも思えないが、もともと沼地のような地形があったのではないかと考えられる。つまり地形的に見て一見弱点のような北側の開析部分も要害性は高かったのである。ということになると、この城で最も防備に気を遣わねばならない部分は、西側の台地続きの部分ということになる。
この城の最大の特徴はこの西側の台地続きにある。ここには大規模な横堀があり、そこには虎口接続のために鍵型の土橋が配置されている。図の7の部分である。
6の郭との間には入江のような8の堀も入れられている。これは進入路を狭めた上に、堀を隔てた郭内側から射撃できるように工夫されているという、なかなか先進的なものである。このような仕掛けがいつ、どのような時期に取り立てられたものなのかについては、この城に限ってはきわめて珍しいことに)明らかである。
下でも述べているように、この城は、天正3年(1575)に、大多喜城主正木大膳憲時が、万木城に対する向城として取り立てたものである。したがって「夷隅の城」でも述べているように、天正3年という限定された時期の正木氏の向城の形態を示す稀な例といえ、その意味で上総の城郭史上、貴重な遺構であるともいえるであろう。
ただし、急造したにしては、この城にはかなりの量の加工が見られ、特に、台地基部とを区画する堀など、敵と対峙している短期間のうちに仕上げられるものなのであろうか、と思ったりもする。正木氏が撤退した後、万木城の出城として、この城を維持、さらに拡張していくといったことがあったのかもしれない。
 |
 |
| 八幡神社の入り口。背後の比高10数mほどの台地上に砦の跡がある。 |
八幡城から見た万木城。夷隅川を隔てた対岸にある。まさに向かい側といった感じ。 |
 |
 |
| 神社から西側に抜ける切り通し(堀切1)。堀切といっていいだろう。深さ5mほど。 |
西側の大堀切。深さ4m、幅は7mほどある。一部には水がたまって水堀になっていた。左に出っ張って見えるのが、虎口の鍵型の部分(7)。横矢の折れにも見える。 |
 |
 |
| 鍵型の部分と郭内側との間に掘られた堀(8)。深さ4m、幅10mほど。 |
内部の民家への入り口の脇にはこんな土塁があるが、これも虎口関連の遺構であろうか。 |
天正3年(1575)、小多喜正木氏と土岐氏は交戦状態に陥り、正木軍は土岐領に侵入、向城を築いて、万木城に対抗した。このことは、天正3年に比定されている12月24日付けの大田新六郎(康資)宛ての、北賢哲(佐竹氏の重臣)書状に「万喜に向いて正大(正木大膳憲時)地利を取り立てらるの由、かくの如き上は、御本意においては程あるべからず候」(万嬉城に向かって正木大膳が向城を築いたので、もうすぐ本意を遂げることができるであろう)とあることから明らかである。
「万嬉への向城」というにふさわしい位置にある城郭とは、この八幡城くらいであり、ここが天正3年の騒乱に際して、向城として取り立てられたものであると見て間違いないところであろう。
軍記物にも正木氏や長南氏が土岐領に攻め込み、向城を築いたといった話が出てくる。これらの話は時と人物(長南氏など)こそ違え、この時の騒乱についての伝承が基になっていると考えてもよいのではないだろうか。
正木氏の攻勢にも関わらず、万木城が落城したとか、土岐氏がこの地から撤退したというようなj形跡は特にうかがい知ることはできない。こんな間近に向城を築かれ、攻め立てられながらも、土岐氏は万木城にこもって敵をやり過ごすことができたのだと思われる。(「夷隅の城」参考) |
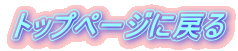
 大野城は鶴ヶ城とも呼ばれ、夷隅川の湾曲部分の内部にある台地を利用したものであり、河川を堀として巧みに利用している。またこの台地そのものが岩盤で形成されており、何ヶ所かに見られる堀切も、岩盤をダイナミックに断ち切ったものである。こういう堀切は正木系、土岐系の城郭でよく見られるものである。
大野城は鶴ヶ城とも呼ばれ、夷隅川の湾曲部分の内部にある台地を利用したものであり、河川を堀として巧みに利用している。またこの台地そのものが岩盤で形成されており、何ヶ所かに見られる堀切も、岩盤をダイナミックに断ち切ったものである。こういう堀切は正木系、土岐系の城郭でよく見られるものである。





 夷隅川にかかる橋のたもとに城はある。
夷隅川にかかる橋のたもとに城はある。



 権現堂に八幡神社があるが、
権現堂に八幡神社があるが、